レイコの主演映画がクランクアップした。その記念に彼女主催でホームパーティーを開くという。ミナミはそれに招かれた。但し、キャストであるコウはほかの出演者達と一緒に会場入りするので、母親とは別行動である。
この所のコウは単独で仕事に向かうことが多い。現場入りや打ち合わせすら一人で呼ばれ、事務所の人と参加する。無論、保護者の同意を得てではあるが。
ミナミにはやはり心配と、また自身色々な現場に顔を出してみたいとの好奇心もあったが、親があまり出しゃばるとロクなことがないとの考えもようやく芽生え、我慢して送り出した。だから、撮影自体に全て同席したとはいえ、以前ほどべったりくっついていたわけでは無かった為に、ややもすると、近頃息子が急に大人に成長したような錯覚さえ覚えていた。
そんな彼女にジンは腕枕をしながら優しく言ったものだ。
「大丈夫。コウ君のことも、きみのことも、ぼくが守るから」
実際その言葉通りだった。ジンの影響力は強い。コウの仕事が順調なのも、その辺りが有形無形に作用していると思われた。ミナミは、いわば恋人と当代最強のコネクションを同時に手中にしたわけだ。
彼女はうっとりと幸福感に目を細めながら、ヒサキの運転する車で会場となる屋敷に向かった。そこは、まるで迎賓館といった佇まいの大きな洋館だった。ここがレイコの持ち物かどうかは、ヒサキにもミナミにも分からなかった。
「ありがとう」
ミナミは言って車を降りると、石畳の道を屋敷の入り口へと歩いていった。それを見送って、ヒサキは車をUターンさせる。と、その先に立ちふさがる者があった。
「やあ」
そこに立っていたのは、ゆったりとした薄手のセーターと、足の長さが際立つジーンズを着た細身の男性。ジンだった。ヒサキは礼儀として車を降りて挨拶した。すると、ジンはそれへ近づきながら、
「キミもどう?」
と、唐突に彼女をパーティーに誘った。ヒサキは丁重に断る。
「いえ、私はお見送りに来ただけで、招かれてはおりませんので」
至極当然の答えだった。が、当たり前でない言動に出たのはジンだった。
「構わないよ、オレから紹介するし。大体、キミだって関係者じゃないか。それに……」
彼は話しかけながら、どんどんと間を詰めてくる。
「世話になりっぱなしのキミに、まだなんのお礼も出来ていないしさ」
「お礼、ですか?」
解せないといった面持ちで、真っ直ぐに相手を見返すヒサキ。探るように、皮肉っぽく言い足す。
「ミナミさんなら……コウ君のお母様なら、今入られましたよ」
それを聞くと、ジンは寂しげに微笑んだ。一度立ち止まった歩を進めて、一メートルを切る距離にまで近寄る。
「そうじゃなくてさ。キミに、話があるんだ」
彼は柔らかな表情の中、真剣な目で語る。
「こうしよう、一緒にここを抜け出して、どこか場所を移そう」
「お仕事の話でしょうか? うちのタレントの?」
「だから、そうじゃなくて。キミに――」
「いえ、それなら、すみませんが、私には仕事がありますのでこれで失礼させて頂きます。それに、あなたがパーティーを抜けられるわけにはいかないと思います」
ヒサキは無表情に言い放つと、車のドアを手早く開けた。その背へ向けて、ジンが叫ぶ。
「あの日、キミが道案内してくれなかったら、オレは今、ここに居なかった!」
ヒサキの動きが止まった。
「初めは分からなかったよ、キミがあの時の子だって。だけどこの前、やっと気がついたんだ。キミが、その……彼女を、迎えに来た時に」
“彼女”と言う前に、彼は少し言葉を探した。名前を出されなくても、ヒサキには誰の事か分かっている。その胸が微かにチクリとした。
「ずっと探してた」
そう言うと、ジンはいきなりヒサキを後ろから抱いた。
「え」
立ちすくむヒサキ。その耳の後ろから、ジンのささやきが襲う。
「今のオレの地位も成功も、みんなあの日から始まった。感謝してる、本当に。キミの……キミの、導きのおかげだよ」
彼は饒舌だった。相手の返事も待たずに独り語りを続ける。
「ねえ、キミはあの日のことを覚えてる? 覚えていないかな。オレは、忘れたことなんて一度もないよ」
ヒサキは黙っていた。その目元にハラリと垂れた前髪が影を作る。
「キミがこの業界に居ると知った時、運命だと思った。ねえ、ひょっとして、キミはオレを――」
「離して」
ヒサキの口がようやく動いた。しかし、その声は小さすぎて、興奮した相手には届かなかった。
「オレを追って、芸能界に――」
「バカにしないで!」
急にヒサキは叫んだ。と同時に、ジンの手を振りほどくや、振り返り様に彼の頬をしたたかに打った。しかし、すぐにハッとして謝る。
「すみません」
この仕事に就いて以来、いや、彼女の人生において、ほとんど初めて人に示した激昂だった。己自身びっくりした位だ。ジンも面食らった。しかし、彼は怒らなかった。
「ううん、悪いのはオレの方さ。ごめん、こっちこそ」
むしろ、今度は悲しげな表情になって、別な話をし始めた。
「……白状するよ。オレ……本当はオレ、辛いんだ」
彼は肩を落とし、日頃のスターなオーラなど見る影もない程だった。
「オレは売れた。けど、それと引き換えに、沢山のものを失ってきた。この世界は、辛いことが多過ぎるよ――」
ジンは再びヒサキの両肩を抱いた。ヒサキはビクリと驚き硬直しながら、赤くなった目で相手を見返す。
「助けてくれ、あの日のように。キミが、キミだけがオレを救える。オレには誰も居ない。キミは特別なんだ。オレと行こう。何もかも捨てて、このまま」
ジンはそこまで一気にしゃべると、口をつぐんでじっとヒサキの目をjじっと見つめた。ヒサキも黙って、見つめ返す。まだ平生の冷静さは取り戻せていない。だが、その動揺を必死に押し殺して、彼女は口を開いた。
「それで……あの人はどうするんですか。……人妻に飽きたから、今度は私ですか?」
その声は微かに揺れていた。ジンは目力を込めて、なお一層相手の目を見つめる。片時も逸らさない。
「違う。……いや、そうだね。ひどいことしてる。オレはもう普通じゃないよ。いつの間にか、すっかり狂っちゃった。この商売、正気でなんかいられないよね……」
「この業界の所為、ですか?」
ヒサキは鋭い目で訊いた。顎を引き、胸の奥に込み上げてくる熱さをぐっとこらえながら。信じていたもの、信じたいものを傷つけること、それは自己否定に繋がりかねない。だが、信念は成長するもの。かつての憧憬からずっと大きくなり、今や独り立ちするまでになった。これは、彼女にとって試練の闘いである。
ジンはすっと手を降ろした。その表情は相変わらず悲しげでありながら、少し冷めた風に言う。
「じゃあ、逆に訊くが、今度の映画にコウ君を斡旋したのはキミだろう?」
それを聞くと、急にキッとなってヒサキは反論した。
「斡旋じゃありません。オーディションの機会を紹介しただけで……」
「同じことだよ。レイコさんの趣味は、キミだってよく知ってるだろうに。そういうの“未必の故意”って言うんじゃない?」
「そんな……! 私は知りません。私はただ……」
「良かれと思って? キミもオレも、特殊な常識にもう呑まれてしまってるんだよ。ねえ、だから……」
議論の果てに、ジンはまたヒサキの肩を抱いた。
「もう抜け出そう、こんな所。オレはもう疲れたんだ。二人でどこか遠い所へ――」
「すみませんが――」
ヒサキは再度彼の手を振り払って言い切った。
「私には大事な仕事がありますので、これで」
彼女は言うと、一気に運転席に乗り込んでドアを閉めた。ジンはその窓をコツコツと叩いて、最後の戦術に出る。
「そうか、一人で逃げ出すんだね。キミが導いた彼の結末を見なくていいのかい」
ヒサキはエンジンをかけた。今はもうジンの方に一瞥もくれなかった。彼もまたこれ以上は止めず、外から寂しそうに声を掛けた。
「……残念だよ。強いね、キミは」
走り去っていく車。それを見送ろうともせず、早々とジンは踵を返していた。その乾いた目は何も語らない。
ヒサキに語ったこと、それはそれで本心だった。同じように、ミナミやコウに約束したこともだ。その時その時で、彼は本気なのである。その刹那的情緒に悪意も策略もなく、自身あくまで純粋だと信じて疑わない。
彼の人格は、幼き頃より注目を浴び、大人に交じって働き、そして性的に嬲られ、慰み者として生きてきたアイドルとしての境遇が、分裂させ破綻させていた。
ヒサキと出会ったあの日も、彼はさる婦人の寝所に入った帰りだった。金と暇を持て余した、還暦過ぎの脂肪の塊である。ジンは“仕事”が済むと、彼女が車を手配している隙をついて逃げ出したものである。その時の彼はもう限界だった。
彼は男娼として、選べない相手と散々交わってきた。女のみならず、男ともだ。垢にまみれた陰唇、きつい臭いのする陰茎、そういうものを舐めしゃぶり、そして肛門を掘られてきた。彼の心と体は、タイガ位の年頃にはもうボロボロだった。
それでも外に出ればキャーキャーと騒がれる人気者で、陰惨な裏稼業など誰も想像だにしない。少年は、メディア上だけの生き物と本当の自分の狭間で行き場を失った。朝から晩まで期待されるままに動き、学校でも“メディアのジン”を演じ続けた。
そんな時である、ヒサキと出会ったのは。彼女は自分を特別視せず、極めて淡々と助けだけをくれた。とはいえ正直な所、この時さほど彼女に感動したわけでもない。ただ、後から思い返した時、その時間だけ全てから解放されたような自由なものであったことに、一縷の希望を見出したのだ。今でも彼は、狂った自分から脱却したい夢と、それを冷笑する現実との軋轢に心を閉ざしているのである。
ミナミと出会って間もなくの頃、母親が死んだ。彼が体をすり減らしてきたのは、全てこの母の命令によるものであった。息子にとり、母は絶対だ。それが死んだ。やっと呪縛から解放されたのだ。
そのタイミングでヒサキを思い出し、助けを求めたのである。あるいは、母親の代わりを彼女に求めたのかもしれない。新しい絶対的指導者を。
本当の所は、ジン自身にすら分からない。彼はもはや無感情の域で、その時その時だけを記号的に演じる役者であり続けるしか生きていけないのだった。
彼の足は規則正しく屋敷へと向かった。そして、表玄関ではなく、別の入り口の方へと回り込んでいった。
その頃、ミナミはその邸内で、狂乱の宴に翻弄されていた。
「なんなの、これは……!」
〈つづく〉
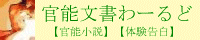
- 関連記事
-





































































































