大物女優との共演話がまとまったのは、ミナミがジンとの関係に腑抜けて、かれこれ半年以上も経った頃だった。この成果はジンの威光によるものではなく、またミナミの暗躍によるものでもなかった。となると、純然たる仕事のオファーということになる。
「コウ君自身の力ですよ」
ヒサキはそう言った。彼女はマネージャーとして“きっかけ”は作ったが、それだけだという。ミナミは有頂天になった。何もかもが上手くいっている、そう感じた。
「レイコさんの映画、決まったんですって?」
早くも噂を聞きつけて、カズエがやって来た。ミーティングテーブルを挟んで、自販機のコーヒー片手に席に着く。同じ境遇の者同士、しばしエールを送り合った後、カズエがこんなことを言い出した。
「ねえ、コウ君って付き合ってる子とかいるのかしら」
「ええ?」
考えたこともない話で、ミナミは現実味がなくて笑った。ところが、カズエの方では冗談でもなんでもなく、
「あら、じゃあアッチはまだ……?」
と、さらに開けっ広げな展開に持ち込もうとする。しかも真剣な面持ちで。
「別に不思議じゃないわよ。この業界にいる子なら普通じゃない?」
そう言われると、圧倒的に説得力があった。タイガだ。身を以て子役の早熟さを知ったミナミである。
そんな彼女の顔をジーッと見つめながら、カズエが尋ねた。
「ねえ、どう? エリカと」
「え、どうって、何が?」
カズエがテーブルに身を乗り出すのに反し、ミナミはちょっとたじろいで背を逸らす。彼女の囁きは悪魔のそれのようだった。
「ふ・で・お・ろ・し」
「え?」
「筆おろしよ」
ミナミは思わず目を見開いて相手を見た。別に言葉の意味が分からなかったわけではない。予想外の申し出に驚いたのだ。
その反応を確かめてから、カズエが静かに言った。
「コウ君、有望だし。あの子もコウ君なら嫌じゃないと思うわ。彼、男前だしネー」
カズエはあっけらかんと畳み掛ける。どこまで本気なのか、からかっているのか。ミナミが混乱していると、カズエはあらぬ方向へと心配し始めた。
「ひょっとして、彼、エリカのこと嫌いかしら?」
「そ、そんなことないわ。多分コウも……エリカちゃん……す、好きじゃないかな……」
しどろもどろにミナミは適当な返事をした。実際には息子からエリカの話など聞いたことがないし、そもそも恋愛話すらしたことがない。
カズエはさらに飛躍した。
「あ、ひょっとして、もうママと?」
「え、な、何を?」
「ママがもう童貞もらっちゃったとか?」
「まさか!」
ミナミは立ち上がらんばかりにして叫んだ。ハッとして、周りを見渡す。幸い近くには誰もいなかった。
「(何言ってるの、この人。親子で……まさか!)」
突拍子もないことを言い出すと思った。ところが、カズエ曰く、不自然なことではないという。やはり業界ではありふれたことだとか。ミナミのウブな反応に、返って彼女の方が意外そうにしていた。
ミナミは今更に落ち着きを装い直して聞き返した。
「エ、エリカちゃんもその……初めてっていうか……経験ってやっぱ……」
だが、同じ土俵で勝負しようと取り澄ましてみても、やはり核心の部分は言い出しにくい。上品ぶるつもりはないが、まだまだカズエの境地には至らないと思った。
幸いカズエは、そんな相手を殊更素人扱いすることもなく、極めて気前よく答えてくれた。ただ、それはミナミが考えている次元とは大きく異なる話だった。
「アハハ、エリカが処女なわけないじゃん。だってもう小六だよ?」
カズエはペラペラと、二年前の処女喪失のくだりまでしゃべりだす。
「“初めて”を誰にやるかってのが大事でしょ」
曰く、バージンは最高のプレミアムなので、高く売らない手はないと。実際彼女は、具体的な名前こそ明かさなかったが、広告業界でかなり力のある男を選んで娘にあてがった。それはカズエ自身が、わらしべ長者のように男を渡り歩いては値踏みして決定したのだという。彼をバックに付けたおかげでエリカの仕事は軌道に乗ったと得意がって憚らない。
「男なんてロリコンばっかよ。あたしらなんか寝るまでが大変なのに、あの子だったら即ハメ。一発で取ってきちゃうんだもん。こっちはやる気なくすっちゅうの」
そう言うと彼女は大笑いした。ミナミもつられて、硬い愛想笑いを返す。“一発”という言葉の真意を、彼女らは確かに共有できた。
ミナミはエリカの面影を思い浮かべた。画面で見る陽気さとは一転して、死んだような灰色の目を地面に落とすスタジオ裏の少女。不自然な程に疲れ切った様子ながら、そこはかとなく艶めいていた。その限りなく子供らしからぬ違和感の正体を、今やっとミナミは悟った。
エリカの“営業相手”は全て母カズエが決め、娘はそれに一切逆らわないという。既に両手に余る人数の男と経験済みだ。驚くべきことに、親子で“営業”をかけることもあるという。
「“親子丼”ってやつ。バカだけど鉄板よね。ま、こればっかは娘を持つ親の特権かな」
現場では母娘で一本のペニスを舐め、また母を犯したペニスで娘が、娘を犯したペニスで母が、と代わる代わるに同じ男と性交する。カズエはそんな男共のことを“変態”とか“鬼畜”と蔑みながら、自身の倫理観については触れなかった。彼女はそもそも、愛娘にフェラチオから何から、セックスの指導まで施すというのだ。
それを我が子の為と思えば、母親はそこまで倫理を捨て去れるのか、とミナミは考えた。また、果たして自分も我が子に同じことを要求できるだろうか、とも考えた。だが、もし子供がそれを望んでいないのだとしたら? 親のエゴを押し付けているだけだとしたら……?
もっとも、想像力の乏しい彼女には、現実の我が子が息子であることから、それ以上に突き詰めることができなかった。
「やっぱ息子さんには新車が良かった?」
下品極まりない表現でカズエが話題を戻す。
「でもさ、絶対コウ君を満足させられると思うよ。エリカ、テクあるし、いい初体験にしてあげられると思うんだけどな」
その瞳におぞましい狂気を見て、ミナミは初めて彼女が怖くなった。自分が足を突っ込んだ世界の闇の深さが、そこにほのめいているようだった。
問われているのは覚悟である。だがそれをミナミが自覚するのは、もう少し先のことだ。
彼女が煮え切らないので、結局子供達の“縁組”は不成立に終わった。カズエは諦めきらずに後日を期しながら、去り際にこう付け加えた。
「まあ、筆おろしにはもうならないだろうけどさ」
〈つづく〉
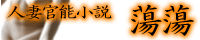
- 関連記事
-





































































































