『山姥今様(やまんばいまよう)』
岳雄(たけお)が目を開けると、そこには見慣れない天井があった。
「いたたっ!」
とっさに起き上がろうとして、彼は体中が痛むことに気づき、またやむなく布団に倒れこむ。
「あっ、じっとしてなきゃだめよ」
そう声をかけたのは、傍にいた女性だった。見れば、自分の母親程の年恰好の女性が心配そうにしている。
「けがしてるんだから、無理しちゃだめよ」
彼女はそう言って、乱れた掛け布団を元に戻した。
「けが?」
その時になって、岳雄はようやく気が付いた。腕に包帯が巻かれている。
「そっちは大丈夫」
腕を見る彼に彼女は言った。
「問題は足ね。多分捻挫だと思うけれど、しばらくは歩けないわ」
岳雄はちょっと足を動かしてみる。すると、右足が異様に重いことが分かった。
どうしてそんなことになったのか、落ち着いて思い返してみる。
(そうだ! みんなとはぐれて、その後、崖から落ちて……)
岳雄は大学の山岳部の一員としてこの山に来た。だが山道を行く途中、靴ひもを直す間にパーティーから遅れてしまうことがあり、慌てて後を追おうとして足を滑らせたのだった。
「ああっ! すいません。ちょっと電話貸して貰えますか」
仲間に無事を知らせるのが先決だ、彼はそう思った。
「大丈夫。ちゃんと連絡はしてあるわ」
と女性は言う。どうして? と問いたげな岳雄の機先を制して、彼女は説明する。
「これ」
差し出したのは学生手帳。
「ごめんね。連絡先を確認するために、リュックの中見させてもらったの。それでね、お仲間の皆さんには、あなたが無事だってことを知らせてあるのよ」
「あ、ああ……」
混乱する岳雄は、ただただ戸惑うばかりである。そんな彼に、彼女は親しげに語りかける。
「びっくりしたわよ。だって、あんな所に倒れてるんだもの。あんな所、普通気づかないのよ」
その時の状況を身振り手振りで教えてくれる女性。その様子から推して、人のいい奥さんといった風体だ。岳雄の緊張がわずかに緩んでいく。
女性が言うには、山菜採りの最中にたまたま地面に突っ伏す岳雄を見付けたのだという。彼女はこの山中に一人で暮らし、登山客に休憩場所を提供しているのだという。名を峰子(みねこ)といった。
明るい彼女にほだされる内、岳雄はようやく肝心な台詞を言っていなかったことに気が付いた。
「あの、ありがとうございました。助かりました」
「いいのよ」
峰子は軽く言って笑う。
「倒れてたのが若い男の子で、ちょっと得した気分だし」
岳雄も釣られてほほ笑んだ。
「さてと。あったかいスープでも用意するわね」
そう言うと、峰子は気合いを入れて立ち上がる。
「おばさん、がんばっちゃうわよ!」
彼女はそう言い残して、部屋から出て行った。
――翌朝。
「昨日はあんまり寝られなかったんじゃない?」
との峰子の問いかけに、岳雄は素直に答えた。
「あの……はい……」
実際ほとんど寝た心地がしなかった。風で揺れる木々の音を聞いたり、窓の外の闇を見詰めたり、部屋の中を見回したりして無為に時を過ごした。
部屋の中は整然と片付いており、小さな机といす、箪笥などが壁に沿って並んでいた。中で、最も岳雄の気を引いたのは、仏壇に飾られた写真だった。そこには、一人の青年が写っていた。
「岳雄君」
岳雄の口元にご飯を運びながら峰子は言った。岳雄は今、けが人の特権として寝たままに朝食を食べさせてもらっている。
「昨日も話したけれど、しばらく天候が荒れそうなのよね。で、けがも一刻を争うような症状じゃないし、しばらくここで安静にして、それからゆっくり下りたらいいと思うの」
この計画は昨晩にも聞いていた。彼の仲間も同意しているらしい。彼とて異論はない。そうした方がいいというなら、それが正しいのだろうと考えていた。そこで、彼はその部屋でしばらく療養することになった。
彼女の言葉通り、その日の午後から雲行きが怪しくなり、夕方には大雨が降りだした。

次第に山は荒れ、壁を叩く雨と風の音が強くなった。昼間でも電気を点けていないと薄暗かった。
岳雄はそんな部屋で終日横になっていた。峰子は何くれとなく世話を焼いてくれる。三度の食事はもちろん、おやつにりんごを剥いてくれたりもしたし、便所にもつきそってくれた。さらには、体まで拭いてくれるのだ。
「本当はお風呂に入れてあげたいんだけどねえ」
しかし、トイレに立つのもやっとだというのに万一のことがあってはと、大事をとってよしたのだった。その代わりに、濡れたタオルで峰子は岳雄の全身をぬぐってくれるのである。
「なんだか本当の息子みたい……」
峰子はぽつりとつぶやいた。その横顔は寂しげであった。後で聞いたところによると、彼女は実の息子を事故で亡くしていたのだった。仏壇の写真はその彼だったのだ。
「ちょうどあなたぐらいの年の頃よ。山で遭難してね。それでね、山に来たの」
彼女いわく、こうして山で暮らすのは息子への供養のためであるという。
「あ、ごめんなさいね、暗い話しちゃって」
「いえ……」
岳雄はなんとか言葉をかけてやりたかったが、どう言っていいのか分からなかった。
――嵐は続く。
外には出られそうもなく、他方岳雄の体調も思わしくなかった。雨風の冷気が傷にこたえる気がする。天候も体調も、ともに前よりひどくなっているように思われた。
「焦っちゃだめ。しっかり寝て治さないと」
峰子はそう言って元気づけてくれる。しかし、そうは言っても一日中寝ているだけというのも退屈なものだ。ここにはテレビもない、本もない。峰子と会話する以外はすることがないのである。
そんな彼にとっての唯一の楽しみは、いつしか体を拭いてもらうことになっていた。拾われて四日目のことである。
初めは恥ずかしいだけだったし、出来れば自分でやりたかった。だが、三回もそれを経験すると、少しばかり図々しい気持ちも湧いてくる。不謹慎とは思ったが、抑えきれなかった。
岳雄を本当の息子のようだと話す峰子の世話は実にまめまめしく、優しかった。これが母性愛というものだとつくづく感じさせられる。それは、とても心地の良いものだった。
おまけに、間近で見る彼女の横顔は美しかった。その白い頬は、彼女の不幸を象徴するように痩せていたが、そこにかかるおくれ毛が妙になまめかしく、岳雄の気をそそるのだった。
彼の視線は、続けて彼女の中の女らしさを探すようになる。束ねた髪の脇からのぞくうなじ、前かがみになった時に見える胸の谷間、後ろ向きにしゃがんだ時の尻の丸み……
(いけない! そんな所を見てはいけない!)
岳雄は自戒した。しかし、肌に触れる指先の優しいタッチが、彼の意識を官能に導くのだった。それだけではない。一日中なすこともなく過ごしていると、性欲が溜まりに溜まるのである。
こんな状況に及んでまで、というより、こういう状況だからこそ性欲が盛んになるのである。
岳雄は勃起していた。
そして、それはすぐにばれた。
「ウフフ」
峰子は笑った。
「元気ねえ」
「すみません……」
岳雄は真っ赤になっていた。
「いいのよ。元気になってる証拠」
峰子は動じることなく、そこもタオルで丁寧にぬぐう。精嚢から陰茎まで、丁寧に柔らかく。
岳雄は恥じらいながらも、不思議と安らいだ気持ちだった。恥をさらけだして、何もかも相手に委ねてしまえる安心感だろう。それにともなって、興奮も極地に達した。
「あ、あの……!」
危ない! と思った時にはもう遅かった。それは、峰子が陰茎と精嚢の間を拭く間、亀頭を手で支えた時だった。
「まあっ!」
彼女が驚いたのも無理はない。噴射した精液は高く上がって、一メートルばかりも飛んだのだ。
ややあって、峰子は、
「すごかったわね!」
と言って笑った。岳雄は、
「すいません……!」
謝るしかなかった。だが内心では、許してもらえるだろうとのあざとい見立てもどこかにあった。男ならではの甘えである。
実際、峰子は怒らなかった。そればかりか、明るく笑ってきれいに後始末をしてくれた。
そういうことが一度でもあると、甘えというのは加速するものである。しかも、峰子は子のない寂しさから、岳雄を我が子のように慈しんでくれる。そういう事情も彼の性欲に拍車をかけた。
「男の子だもんね」
彼女がそう言ったのは、彼がトイレに立った時にも勃起しているのが分かったからだった。着させてもらっているパジャマの上からでも、勃起しているのはすぐにばれてしまう。
自分で何とかすればいいのだが、枕元にティッシュを置いてくれとは中々言い出しにくく、それでトイレの最中にと思っていると、そこへ向かう前にはもう勃ってしまっているのだ。
「ごめんね、こんなところ見られたくないよね」
「あ、いえ、そんな……」
峰子は気を使って言ってくれたが、岳雄からすれば見当違いな話である。彼の心理としてみれば、悪いのは自分なのである。
「でもびっくりしちゃったわ。男の子って、すぐそういう風になるのね」
峰子は岳雄の反応について、微笑ましく思っているらしかった。亡き息子を偲び、同じ年頃の岳雄に彼の姿を重ね合わせているらしい。すると、なんでも許せてしまえるようなのだ。
だから、岳雄が彼女の胸に手を触れた時も当然のように咎めなかった。
「もう、いたずら? 悪い子」
口では叱っても表情は笑顔である。岳雄がそういう挙動に出たのは、完全に峰子を性対象として見ているという宣言にほかならなかったが、彼女はそうと知りながら戯れ返すのだ。
やがては、体を拭いてもらう時、岳雄は勃起し、それを慰めてもらいながら彼女の体を撫でるのが日常になった。岳雄は歩くのはまだ難儀だが、手は十分使えるのである。
ほどなく彼はそのいたずらによって、彼女の乳房を獲得することに成功した。
「まあ! そんなにお兄さんになっても、まだおっぱいが欲しいの?」
峰子の心にはいささか倒錯が生じているようで、彼女の中の亡き息子は、時に小さな子供にもなるらしい。結果、岳雄のことを次第に何もできない甘えん坊の息子として扱うようになった。
岳雄もまた岳雄で、どんどんとその流れにはまっていき、何の恥ずかしさも感じなくなる。
ついには、食事の折にも堂々と所望するようになった。
「あら、おっぱい?」
ねだられると峰子は断らない。彼女は食事の合間に乳房を露出し、食べ物を口に運ぶのと同じように乳首を彼の口に含ませた。その上、彼の男根まで握って。
「あら、苦しいの? かわいそうに」
彼の勃起を握る時、峰子はそう言うのが常だった。射精ができなくてかわいそうという意味だろうか。本気でそう思っている風なのである。
我が子への愛情だとしても異常なものだが、深い喪失感が彼女をそこまでの過保護に追い込んだものだろう。
そんな二人が男女の仲になるのに、もはや時間はかからなかった。
「アアッ! 岳雄! 岳雄!」
峰子は岳雄の上にまたがって、激しい突き上げに啼いた。
「ごめんね! 母さんが相手でごめんね!」
彼女が言うには、本来ガールフレンドとするべきことを、やむにやまれぬ事情から母が代理で行うことを申し訳ないというのである。
「か、母さん! ああっ! 母さんがいい!」
岳雄は叫んだ、峰子のことを母と。峰子は満面の笑みで答えた。
「アアッ! 嬉しい! 母さんも岳雄がいいわぁ!」
やがて岳雄が峰子の中に精を吐き出すと、彼女は彼の上に倒れ込み、二人は裸でべったりとくっつきあって、濃厚な口づけを交わすのだった。
それからはセックスが日常になった。
「母さん」
岳雄はトイレに立った時、勃起した肉棒をすり寄せて峰子に甘えた。
「あん、ダメよ。お夕飯が済んでから、ね?」
峰子はやんわりと彼を立たせると、
「ほら、今はその前に、お口できれいにしましょうね」
と言って、彼の陰茎を口に入れた。
「おしっこちゃんと最後まで切らなきゃだめよ」
峰子は膝まづいて、放尿後の息子の肉棒をしゃぶる。これも親子の愛の一環として。
またある時は、峰子がこんなことを言った。
「今日のおかずはとっても精の付くものよ」
岳雄はごくりと唾を飲み込む。
その後、彼の部屋からは峰子の喘ぎ声が絶えなかった。
「アアンッ! 岳雄ぉ! 母さんそんなにしたらおかしくなっちゃう」
「母さんのマンコ気持ちいいよ!」
岳雄は彼女の体を下から激しく上下に揺さぶる。峰子は髪を振って乱れる。二人の合体はいつも騎乗位だ。
「イクゥ! イクゥッ!」
峰子が啼けば、
「僕も! 母さん、僕も!」
そう言って、岳雄の腰つきはより強くなる。やがて、二人はぐったりとして離れた。
ハアハアと息を吐きながら、峰子が言う。
「岳雄ががんばり屋さんだから、母さん大変だわ」
「だって、母さんの料理食べたら、こんなに元気になっちゃったんだもん」
ほら、と岳雄が示すと、彼の肉竿はもう勃起していた。
「まあ! もうなの?」
峰子は目を丸くする。
「うん、でもちょっと休もうか? 母さん疲れちゃうもんね」
「何言ってるの?」
岳雄の気遣いに峰子は奮起して起き上がった。
「岳雄ががんばってるのに、母さんだって負けてられないわ!」
そうして、彼の男根にうっとりと手を這わす。
「偉いわね、岳雄。こんなに立派になって。こんなに固くておっきくて。岳雄のお嫁さんになる人は幸せね。毎日こんな美味しいおチンポ食べさせてもらえるんだもん」
そう言うと、峰子はそれをぱっくりとくわえた。
「お嫁さんなんかいらないよ。僕は母さんとだけオマンコするもん」
岳雄の台詞に峰子はうっすらと涙を浮かべてほほ笑んだ。
「ばかねえ、岳雄ったら」
「うそじゃないよ! だって、母さんすごく気持ちいいもん! 僕、母さんのオマンコ大好き!」
「母さんも好きよ! 岳雄のおチンポ君、大好き!」
二人は愛を語り合って、再び一つになった。岳雄は峰子の背中を抱きしめ、腰を振りながら彼女と舌をからめ合う。いつ果てるともない情事は、いつ癒えるとも知れない岳雄の傷とともに、いつまでも続いた。
「まだ見つからないんですか!」
母親の絶叫がこだまする。
「奥さん、落ち着いて」
救助隊の男性が肩を抱いてそれを押しとどめる。彼女はそれを振り払って、
「これが落ち着いていられますか! 手がかりもないんですか!」
再び叫ぶ。
「かわいそうに」
陰で見ていた男がつぶやいた。
「山岳部の連中もすっかり落ち込んでしまっているし」
「うん……」
もう一人の男がそれに応ずる。
「なんでも、ちょっと目を離したすきに忽然と姿を消したらしい」
「こりゃ、山姥だな」
突然そう言いながら近寄って来たのは、一人の老人である。
「山姥?」
「そうじゃ。昔々、子供を山で亡くした母親がな、後を追って一人で山に入ったんじゃ。それ以来、山で迷った男を時々連れ去るという……」
「なんだい、迷信かよ」
男達は呆れながら首を振った。
「迷信じゃないわい! なんでも奴は、しきりに自分を母親と呼ばせようとするらしい。助かった者もおるんじゃがな。そいつは一遍も母親とは呼ばんかったそうじゃ……」
老人の話を、男達はもはや聞いていなかった。彼らは一様に、視線をテーブルの上に落としていた。
そこには一冊の学生手帳が乗っていた。岳雄の名が記されている。
岳雄生存の連絡は、まだ来ない。
<おわり>


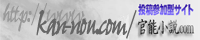
- 関連記事
-
テーマ:官能小説 - ジャンル:アダルト




































































































