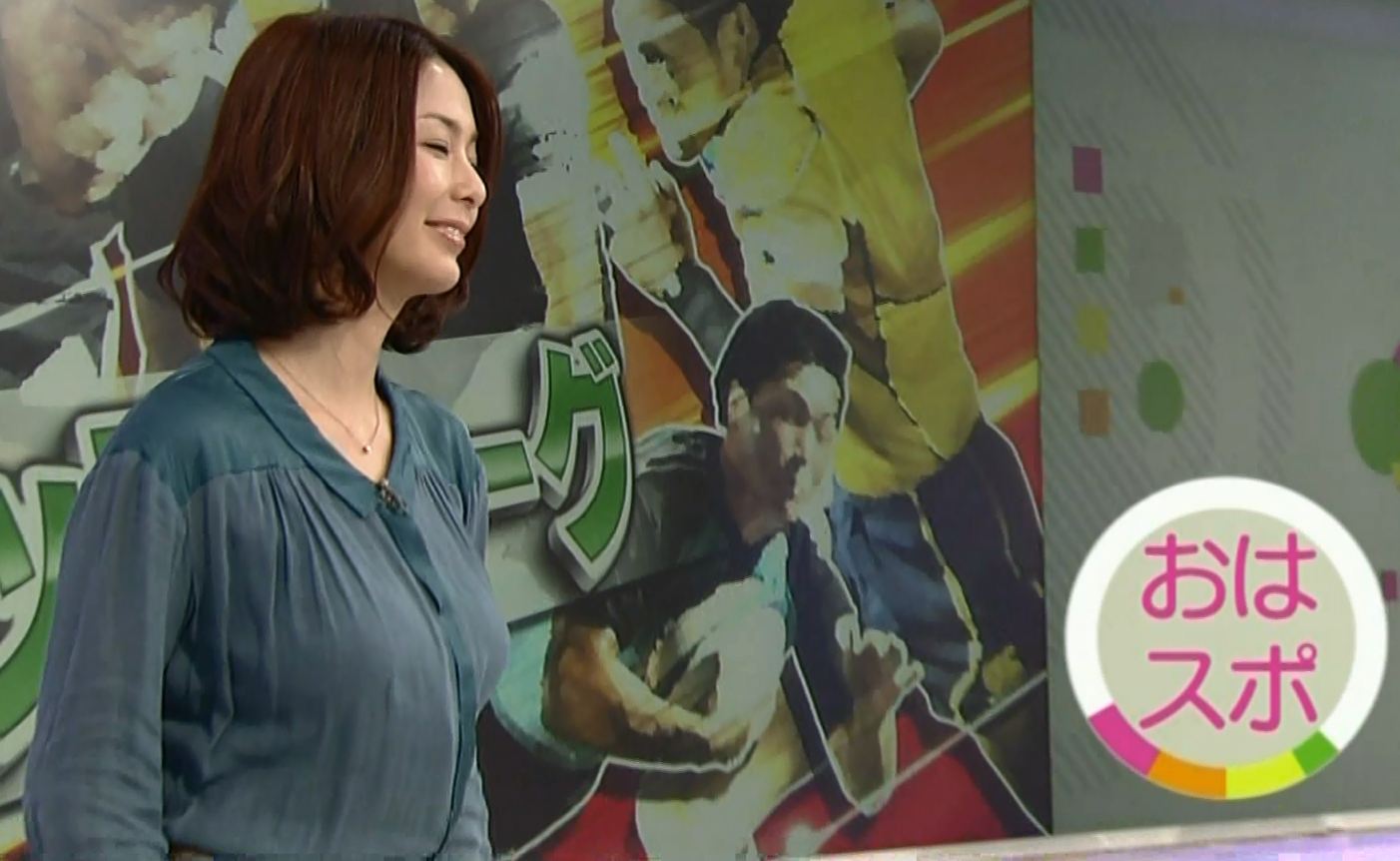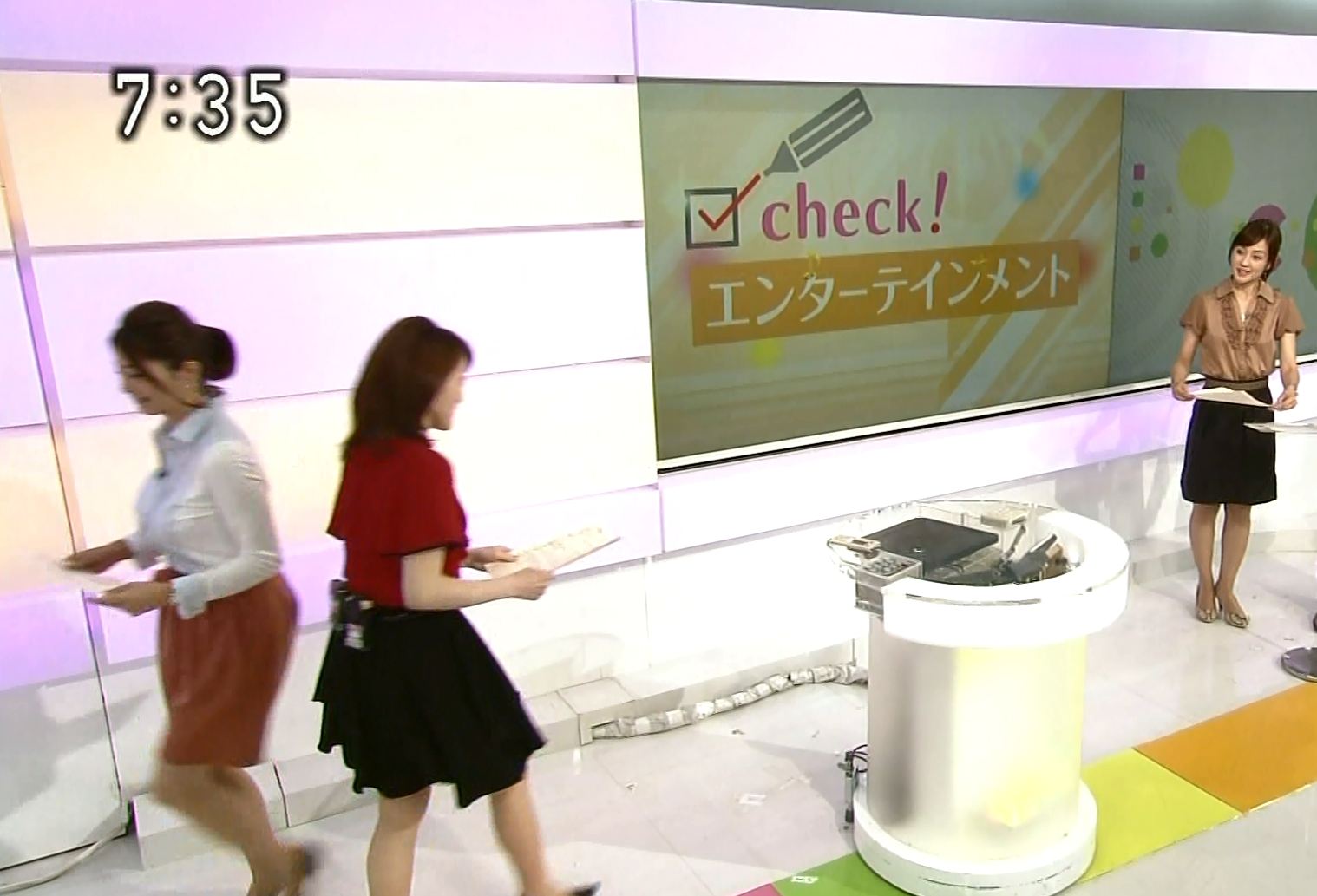おことわり
 このブログには、エッチなことがたくさん書いてあります。まだ18歳になっていない人が見ていい所ではありません。今からこんな所を見ていると、将来ダメ人間になってしまいます。早くほかのページへ移動してください。 >googleでほかのページを検索する< なお、掲載している小説はすべて虚構であり、実在の人物・団体等とは一切の関係がございません。 |
お知らせ
「オナこもりの小説」は、エロ小説を気ままにアップしていくブログです。たまに、AV女優や、TVで見た巨乳のことなども書いています。左サイドにある「カテゴリ」から、それっぽい項目を選んでご覧ください。
       小説には、連続作品と一話完結作品があります。連続作品は、左「カテゴリ」の各作品名より一話から順番に読むことができます。また「目次」には、各作品の概要などをまとめた記事が集められています。 ■連続作品 ◆長編作品 ▼「子宝混浴『湯けむ輪』~美肌効姦~」 ◆中編作品 ▼「大輪動会~友母姦戦記~」 ▼「青き山、揺れる」 ▼「師匠のお筆」 ◆オムニバス ▼「母を犯されて」 ◆短編作品 ▼「育てる夫」 ▼「最後の願い」 ▼「ママの枕」 ▼「ブラック&ワイフ」 ▼「夏のおばさん」 ▼「二回り三回り年下男」 ▼「兄と妻」 ■一話完結 ▼「ふんどし締めて」 ▼「旧居出し納め・新居出し初め」 ▼「牛方と嫁っこ」 ▼「ガンカケ」 ▼「祭りの声にまぎれて」 ▼「シーコイコイコイ!」 ▼「サルオナ」 ▼「母の独白」 ▼「童貞卒業式」 ▼「お昼寝おばさん」 ▼「上手くやりたい」 ▼「珍休さんと水あめ女」 ▼「栗の花匂う人」 ▼「乳搾りの手コキ」 ▼「妻つき餅」 ▼「いたずらの入り口」 ▼「学食のおばさん便器」 ▼「山姥今様」 ▼「おしっこ、ついてきて。」 ★作品一覧 |
|
続きを読む
テーマ:アイドル・女優・女子アナウンサー - ジャンル:アダルト |
|
「おはよう」の挨拶より先に「スポッ」と入っちゃう番組『おはスポ』から、朝一の巨乳をヌキヌキ。 毎朝の帯枠に堂々とボインボイン現れ、巨乳市場の王道をほしいままに独占する杉浦アナ。 彼女のそれは“角度によって”などの“隠れ”的なものでなく、正味の一品です。  上から見ても安定の巨峰。 お辞儀をしてもこの出っ張り。服の中でどんな風に移動しているか、あなたにも分かりますよね。 向かいの彼女も羨望の眼差し。 あ~あ、相方はとうとう降参してしまいました。“トップリーグ”にいる者との実力差は歴然。 それでも手を抜かず、スケスケシャツを着てくるほどの念の入れようはさすがです。 彼女自身の“トップ”も気になるところ。 スケスケトップで嬉しそう。 と思いきや、これはもしや……? あ、やっぱりね。スケスケを見られて感じちゃったんだね。 割と感じやすいタイプの巨乳ちゃん。 「こすれるたんびに勃っちゃう」んだって。 原稿から離れた両手は思わず股間の方へ。そして股間は角っこへ。 コラコラ、生放送中だよ。そんな満足そうな顔しないの。 生がイイのは分かるけどさあ。 登場時もまずはここから見切れてくるという頂き。立派な主張です。 毎朝のことながらガン見する対岸の人。 そりゃ仕方ないですよね、あんなにタプンタプンされちゃあね。 ふう、やっと到着。 いつも過激なボール運動、お疲れ様です。 これぞ真のYC(横乳)。 みんなしっかり見てますよ。 そして爽やかなこの笑顔である。 帰りのドリブルでは、対戦相手もやっぱりガン見です。 この激しいバウンドの前には、先輩アナもさすがに勝ち目がないようで。 勝利して優々と去る者、敗者同士目と目を合わせる二人。 ここまで圧勝されると、もはや悔しくもないでしょうね。 朝に相応しい爽やかな一戦でした。 
続きを読む
テーマ:アイドル・女優・女子アナウンサー - ジャンル:アダルト |
|
「もっとこっちに来て」 いづ美にささやかれ、祐子は全身を責め貫かれたまま前進した。夢見心地の歩みだった。その歩みは、ちょうど緑川の頭部をまたぐような位置で止まった。 緑川は昇天後すっかり放心して、いまだ小刻みに痙攣したまま転がって、まるでただの肉塊のように無用の長物となっている。さっきの射精なしのエクスタシーというものは、余程の衝撃をもって彼を襲ったらしい。 しかし、誰も彼を心配することなく事態は推移していく。 風呂場に響く、ピチャピチャとかクチャクチャとかいった音は、全部祐子の体から発せられるものだ。 (イくっ……イくぅ……っ!) 祐子の頭の中は、もうそればっかりである。もはや一人では立っていられず、周りの人間の世話になりっぱなしだ。仕舞いには、緑川の頭に股間を乗せんばかりにまで腰砕けになってしまった。 そんな彼女に、いづ美がまた囁きかける。 「いいのよ祐子さん。ほら、出して」 彼女の指の動きに合わせて、ピチャピチャという音が跳ねる。やがて、ピチャピチャはバシャバシャに変わった。そして、 「ア、ア、アアァー……!」 汁の音にまぎれて、祐子は遠くに向かって咆哮していた。何かを諦めるような感覚、そして腰が軽くなっていく感覚が彼女を包む。 ピシャーッ! ピシャーッ! と、股間からは透明な液が連続して噴き出した。それがことごとく、緑川の頭から肩の辺りへと降り注いでいく。 そのことに気づいているのかいないのか、緑川はただ口をパクパクさせながら痙攣しているだけである。まだ祐子に謝っているつもりだろうか。 「あらあらあら、たくさん出るわねえ」 嬉しそうに笑いながら、いづ美が言った。彼女の右腕は、すっかり汁まみれになっていた。 やがて、その腕が離れれば、途端に祐子はその場に座り込んでしまう。黄本の腰も離れ、彼女は一遍に支えを失ったのだった。途中緑川の頭部にしたたかに股間をぶつけながら、彼女はペタリと床に尻をついた。 と、そこへ、この機を幸いと赤井が近寄ってくる。 「祐子さん、俺も出るわ」 彼は激しくしごきながら亀頭の先を祐子の鼻横に付けると、そのまま勢いのよい射精を彼女に見舞った。 すると、間髪入れないタイミングで、僕も、とばかりに白木も射精を始める。元来趣味の彼であるから、もちろんここも顔面に向けたものである。 さらには、背中の方から黄本が、頭をまたいで祐子の額に同じく精液を放出していく。期せずして、ここに三筋の精液が出そろうこととなったわけだ。 男たちは眼下に見下ろす祐子の顔へとそれぞれの蛇口を向け、一斉にエクスタシーに達する。もう何度も出しているため、さすがに濃い濁り汁が大量に出るわけではないが、それでも粘液にまみれた陰茎を、彼らは思い思いに彼女の顔面に擦りつけていった。 (アア……) 祐子はアクメの高波に揉まれながら、ひたすら幸福に包まれていた。彼らの体型上、つまり大きく出っ張った腹や太すぎる腿などの故に、三本の肉棒がきれいに顔の上に乗るのは難しく、そのため彼女の肩辺りまで巻き込んでの押し合いへしあいが発生するのだが、それがまた幸福感を倍加させる。肉の圧迫、ムンムンとする熱気、男であるのみならず力士である彼らからの奪い合いの中で、祐子の絶頂は果てしがなかった。 ある者は髪の毛を、またある者は口内を犯しにかかる。さらにまたある者は、いつの間にか放 尿まで始めた。いつもの黒岩の代わりにということであろうか。すぐに他の者も続いていく。薄黄色い液のシャワーが、髪、額、まぶた、鼻腔、口腔と、余すところなく濡らしていく。 「ンンゥー……ンハアァー……ッ!」 祐子は喜悦にむせんだ。息の苦しいのが、返って気分を盛り上げる。 (アア……幸せ……!) 三本のペニスから三筋の小便、祐子はそれらの受け皿として己が顔を開放しながら、幼少より積み重ねてきた密やかな趣味をも全て解放し、ありのままの自分をさらけ出して昇天できることに、絶対的な満足を感じていた。 * 宴が終わり、彼女は家路につく。車窓から見える景色は、もう夕闇の中だ。 「泊まっていきなさいよ」 別れ際にいづ美の言った言葉が後ろ髪を引く。だが、祐子は帰らねばならなかった、彼女の日常に。 体中くたくたに疲れている。一方、足取りは宙に浮いているようにフワフワしている。体も心も温かい。 祐子はバッグを抱きしめた。その中には、先程貰った土産が入っている。ビニール袋の中に大量の使用済みコンドーム。ずっしりと重い。次はいつ来られるか分からないから、貴重なコレクションだ。 土産、といえばもう一つ、それは彼女を取り巻くにおいだ。男たちの汗、精液、小便、これらは体中に染み付いており、何度風呂に入ってもしばらくは取れることがない。一種のスリルである。 「ふう……」 うっとりとため息をついて、祐子は衣を内側へ引き寄せた。家に帰って、寝て、起きて、その頃には、今日の肉欲もすっかり衣で覆ってやらねばならない。それが彼女の生き方である。 明日からまた真面目な顔をして、彼女はテレビの中に帰る。 <おわり> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50)、 (51)~(60)  |
|
「祐子さん、パイズリ! パイズリやって」 その言葉とともに、祐子の眼前に太い肉棒がボロンと投げ出される。今の今まで彼女の中に入っていた肉棒だ。まだ固く立ち上がって元気満々である。 祐子はほつれ毛をさりげなく直しながら、そそくさと膝立ちをして、赤井の足もとに近寄っていった。そうして自前で豊乳を持ち上げ、その谷間で肉棒を挟みこんでいく。 初めは思い切り胸板から押しつけていって、男性のシンボル、玉袋までを含む全体を一気に包み込む。目算を誤り勢いがつき過ぎて正面衝突した格好だが、半ばは確信的でもある。男性全体を自身の乳腺で感じたいのだ。また、衝突の瞬間丸い脂肪がバウンドして、相手の股間にずっしりとした衝撃を与えるのが、彼女のこの行為にかける自信のほどを象徴してもいた。 祐子の乳は大きい。俗に言う、“巨乳”の呼称にぴったりである。くどいようだが、彼女はこの豊満な乳という武器によって成り上がってきた観すら否めないのだ。もちろん、他の器量のおかげもある。が、やはり“巨乳アナ”の称号は伊達ではない。 その武器は、その存在自体で有効ではある。容姿を彩る、大きなアクセントだ。しかし、彼女はそれを、もっと直接男性に対して使用しようというのである。それが、いわゆる“パイズリ”という技で、祐子はこれを得意としていた。 宿命というものであろう。豊かな胸に生まれ育った女として、男を悦ばせたいと思った時、この行為に及ぶことは自然な流れだった。男の方でも少なからず彼女の胸に目を付けて付き合うわけもあり、その結果、男にねだられ、仕込まれて今日まで来たのである。 また、乳房も乳房で、男に揉まれることで成長が加速するぐらいのことは周知の通りだが、さらに男根というフェロモンの塊を直接くっつけることで、もっと大きくなりもし、かつ、いつしかそれを挟みやすい形状に進化していったのであった。 かくして、祐子の乳房は性の玩具となったのである。妄想の空で彼女のそういった姿を描きつつ、しかし現実にはそんなことはやらないだろうと――実際、ニュースを読む彼女の堅物そうなスーツ姿からは、余りに懸隔のある様ではあった――一般の視聴者は考えるわけだが、どうしてどうして、日常の行為としてそれをなしている彼女なのである。そして、彼女に言わせれば、それは巨乳にとって当たり前の仕事だというわけであった。 仕事は滞りなく進行していく。さっきぶつけた胸をゆっくりと上下させる。圧迫された乳肉が赤井の股間の上を滑る。まずは乳房全体の表面で、男性自身を愛撫するのだ。その間、陰茎は下腹に押さえつけられて上空を見上げている。その表面は、先程までの亜矢子や祐子との交わりで濡れたままだ。おかげで、よく滑る。 そのヌラリと伸び上がった幹部の裏の筋を、凝り固まって尖った乳首がなぞり上げていく。祐子にはゾクゾクするほど気持ちの良い瞬間だ。雄々しい固さに乳首で触れられる悦び、乳を性器のように使える悦びが心に充満していく。自分ならではの乳房の大きさが、これほど役に立つことないだろうと思う。 そういえば、かつて彼女の胸はこんな風に命名されたことがあった。 「乳マンコ」 まさに性具として使用する乳という意味だ。これを言ったのは緑川。例によって祐子を罵る意図で言ったものである。 「チンポ専用の乳だな、この乳は。あんた、アナウンサー辞めて、これ仕事にした方がいいんじゃないの。これしか才能ないんだし」 ひどい言われ様だったが、不思議と腹は立たなかった。祐子自身、妙に自覚する部分があったからである。乳房で女性器の代用をするのは、確かに変なことだとは思う。しかし、実際問題、巨乳の役立て方というのはこういう形しかないのではないかとも思うのだ。そして、少し情けない恰好だとは思うが、乳房でペニスを挟んでいる時、これこそが自分のあるべき姿だとも感じるのである。 何より、嬉しいのだ、乳房でペニスを悦ばせられることが。谷間の中にペニスがある時、彼女はそれをまるで息子のようにかわいく思うし、一方で、その固さが逞しくも思え、それに身をくっつけていることで安心を覚えることもある。また、単純に肉体的に気持ちいいというのもある。 パイズリしか能のない女、自分はそういう女だ、と自嘲することもある。だが、それで良かったとも思う。そう思える程、彼女にとってこの行為は意義あることなのである。 祐子は、母乳を搾り出すように脂肪を持ち上げると、もう片方の手で男根を握り、夢中で両者を擦り合せた。 「ハアァ……」 思わず唇を震わせる。擦れる瞬間が気持ちいい。だが、もっといいのは何と言っても挟む時だ。祐子は乳肉を左右に開くと、上向きの剛直を一気に胸板へと沈め込んだ。覚えたての頃に比べ、随分と挟みやすくなった。形状・技術の向上に加え、年齢的な変化もあるだろう。胸の位置が下がり、脂肪が垂れてきたことでパイズリ向きになった。 挟んだら、まずは脂肪の塊を互い違いに動かして、間の男根を弄ぶ。上から見ると、亀頭が右左、左右と半回転する様子が分かる。柔肉の中では、竿がツルツルと滑っているのだろう。時折粘液の、ネチャッという音が聞こえる。 続いて、肉竿に沿って二つの肉塊を上下に動かす。これこそまさに、女性器と同じ役割である。胸の谷間に挿入した男根は、そこを女陰と見なしてピストンするわけである。もっとも、動かすのは女の方だ。女は持ち上げた乳房を上下に振って、ペニスをこする。谷間から剛直をこぼれ出させないようにするのは、中々に骨の折れる仕事だ。それを祐子は慣れた手つきでこなしていく。 男が動く場合もある。女が寄せて待つ胸の狭間へと垂直に、男根を文字通り挿入するのである。今の状況のように男が仁王立ちしている場合は、このやり方の方が容易い。 (あぁ……乳マンコ……) 我が胸に入るオスの生殖器を、祐子は満足げに見守った。肉をかき分けかき分け、ずず黒い棒が赤茶色の乳輪の合わせ目を通って、生白い皮膚の双丘の中へと消えていく。その後、出たり入ったりを繰り返す。時々滑り過ぎて胸板を縦に移動し、真っ赤な亀頭が鎖骨の近くへとこんにちはすることもある。とんだやんちゃ坊主である。 「ンフ……」 祐子は、目を細めて彼との戯れに酔った。暴れん棒は胸の谷間を完全に女陰と認めたようで、丸っきり子作りよろしくピストン運動を繰り返す。ペニスとヴァギナならぬバストとの交尾である。動く度、股間周りがパフパフと肉の丸みにぶつかって、その表面を波立たせる。中央に寄った乳輪は、陰毛の中に埋まったままだ。 さりげなくよだれを垂らしてみる。下唇の輪郭を乗り越えて、ツーッと一本の糸が流れ落ちる。それは下の山肌に着地した。胸を上げ下げして、上手くその汁を狭間の方へと移動させる。要は、追加の潤滑液というわけである。 亀頭も汁を吐いていたが、生憎それは帽子の中に溜まるのみであった。本来ならば、それのとろみも潤滑液になるはずなのだ。その上、男の精のにおいが直に胸に染み付くはずなのだ。祐子は些か残念であった。 かつて、白木が谷間で自失した時のことを思い出す。その噴き上がりは勢いよく飛んで、祐子の顔面にしたたかに当たったものだ。その時祐子は、乳房が最後まで“乳マンコ”たりえたこと、すなわち乳房の性交で陰茎を射精に導けたことに誇らしさを感じていた。陰茎が、胸の谷間を膣だと認識してくれたと理解したのである。その時感じた高揚感たるや、実際の交合とはまた一味違った、独特の良いものであった。 今もそのことを思いだしながら、祐子はうっとりと胸で肉棒をしごいていた。このまままた射精を味わいたいものだ、などと考えながら。もはや、傍観者の存在をすら忘れていた。 ところが、その忘れていた者が、思いがけず急に存在感を復活させてきた。 「へえ……それがパイズリっていうんだ」 かの者は言った。その声音には、好奇心と、そしてまたしても軽い侮りの情が浮かんでいた。 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |
|
命じられるままに、腿を自ら支えてVの字に大開脚する。発情したヴァギナが丸見えになる。緑川はそれを撮影すると、そのまま合体するのかと思いきや、今度は別な体位を所望してきた。祐子は素直に従って、四つん這いになる。しかし、それでもすぐに合体とはならない。 「おチンポ入れて下さい……」 まだアピールが足りないのかと思い、彼女は頼まれもしないのに卑猥な言葉を述べた。これまた自らの手で尻肉を開き、その谷間を明るみに露出しながらだ。 「入れてぇ……早くぅ……」 いかにも尻軽な風を演じながら、祐子は懇願する。そうする間にも、緑川は携帯を股間に近づけて、その中を撮っているのだ。その恥ずかしさを紛らわす意図もあってのことだった。 「これがヤリマンのマンコだ」 彼は一人で解説しながら撮影を続けた。写真なのか動画なのかは分からないが、どっちみち祐子の性器が大写しになっているのは事実だ。 「きったねえヤリマンだな。やり過ぎなんだよ」 彼はさらにこう評して、例によって祐子を辱める。これに対し言われた本人は、身を縮こまらせてそれに耐えた。 「すみません……」 謝罪の言葉すら口にした。すると、これによって相手は次なる凌辱案を思いついたらしい。 「そうだよ、謝んなきゃいけないよなあ。テレビ見てる人は、あんたがヤリマンだってこと知らないんだから」 こうして祐子は、また以前のように破廉恥な謝罪会見をさせられる破目になった。 「わたしはヤリマンです――おチンポ大好き女です――おチンポハめてもらうしか能のないメスブタです――体を売ってレギュラーを貰いました――最低の女子アナです――」 「今まで偉そうにニュースなんか読んですみませんでした――これからは引退して、マンコに専念致します――わたしは殿方の公衆便所になります――おチンポだけを食べて生きて参ります」 次々と促される台詞を、ひたすら朗詠していく祐子。これがマインドコントロールというものなのか、彼女の頭の中はグラグラと揺れて、それと同時に例えようもない高揚感が身内に満ちてきた。 ついには、土下座までさせられてしまった。額を地につけ、その上後頭部を踏みつけられさえして、根拠のない謝罪を続けさせられる。 「汚いヤリマンで申し訳ございません――こんなブスの汚いヤリマンは、肉便器になるぐらいしか道がありません――おチンポの入れ物になるのが夢です――」 さらに緑川は、次の文句を彼女に伝える。が、この時ばかりは、珍しく祐子が躊躇した。 「当然だろ、肉便器」 彼は言って、さあ早く、と彼女を促す。そうされると、もう彼女は受け入れざるを得なくなってしまうのだった。 「これからカメラの前で中出ししてもらいます――ヤリマンにおチンポ汁入れられて、祐子は妊娠します――これからは大きくなったお腹でテレビに出ます――」 堂々の妊娠宣言だった。仕事への責任感から、これまで彼女が回避していたことである。もっとも、この動画や写真が流出すれば、再びテレビに出られるとは思われなかったが。 「じゃあ入れてやるか」 ようやく緑川は許しをくれた。祐子の顔がほころぶ。その表情には、将来への不安など微塵も見えなかった。が、ほんの近い将来への障害は、思いがけず発生した。 「じゃあ、好きなように入れろよ」 そう言って、彼は立ち上がった。本来ならば、願ってもない一言である。しかし、これが思いのほかの難題であった。 “好きなように”とは言ったが、相手は立ったままである。寝てもらうか、座ってもらうかしないと、挿入には都合が悪い。だが、彼にはその配慮がまったくない。言うことも聞いてくれない。明らかに、祐子を焦らして愉しんでいるのだ。 それでも祐子は健気に、はじめは尻の方から相手の腰に近づいていった。計画では、後ろからズッポリとハまるはずだった。ところが、これがうまくいかない。いかに力士の中では小兵の彼といえども、足をピンと伸ばしたままの状態では届きそうもなかった。せめて中腰にでもなってくれればいいのだが。 彼女は、しばらくそうして頑張ってみたが、何度やっても無理なことを知ると、ついに焦れて音を上げた。 「ンン~……入れて下さい……」 まるで、駄々っ子のような口ぶりだった。しかし、緑川は無視して、相変わらず棒立ちのままだ。そこで、祐子はまた、地べたに両手をついて懇請した。 「お願いします……おチンポ入れて下さい……」 それでも相手は動かない。祐子はいらぬ恥をかいた。自分の計算のあざとさを見透かされたようで、一層恥じ入る。仕方なしに、もう一度挑戦に向かう。 今度は向かい合わせになって、自分の右足を抱え上げて試す。が、もうちょっとという所で届かない。途中、右足が疲れてきたので、左足に替えた。やはり同じことだった。 最終的には、相手の体によじ登っていった。最後の手段だった。相手の肩に手をかけて、両足をもがき、足の裏で相手の膝や腿を蹴る。される方としては、それなりに痛いのではないだろうか。しかし緑川は、むしろ彼女の必死さ加減を笑う方に忙しかった。 祐子は、そうやってあがきながら、一方で別なことに思いをはせだしていた。それは、緑川の、いや力士の肉体の心地よさである。何度も肌を合わせはしてきたが、このような取っ組み方をしてみると、いつも以上に相撲を身近に感じることができた。胸を借りる、とはよく言ったものだ。これは、ちょっとしたぶつかり稽古だった。 しかし、あくまでも目的は一つである。彼女は、かなり荒れた呼吸をしながら、ようやくのことで、彼の首に手を、腰には足を巻きつけることに成功した。冷静にみると、何とも間抜けな努力であった。 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |
|
「何? 指チンポだ?」 いかにも呆れたという口調で、緑川は言った。 「そんな名前で呼んでんだ?」 彼にとっては意外な収穫であった。いな、彼ならずとも想像だにしなかったことだろう、妙齢の女性の口からそんな単語が出てこようとは。しかも自発的にだ。 祐子自身びっくりである。彼女は自分で言っておきながら、その後で、サアッと頬を赤らめた。一方で、体内の興奮は異常なほどに盛り上がっており、それによって沸騰する血液が、彼女をして一段と破廉恥な行動に走らせていく。 祐子は、両の手の中指と薬指をそれぞれ揃えると、その四本の指で、小陰唇を両側にめくり広げてみせた。シェークされた粘液が、その合い間からトロリと漏れいずる。 「すげえな。マジでど変態だな」 緑川は言った。 「アハアァァ……」 返事とも何ともつかない、大仰なため息を吐く祐子。淫獣の咆哮とでも呼ぶべきだろうか。その水蒸気の一粒一粒が、まるで愛液なのではないかというほど、彼女は今性の権化と化して見えた。 「さすがにヒくわ」 冷笑を浮かべて、緑川は言った。だが、その言葉とは裏腹に、彼の肉茎はいきり立っていた。オスとして、目の前の肉に素直に反応しているのである。祐子が思い切った甲斐のあったというものだ。 もっとも、何もかもさらけ出して本気の自慰に走り出した彼女は、もはや賞品という目標を見失っていた。彼女は、クリトリスを親指でこねくりながら、ヴァギナを縦横無尽にかき回して、ひたすら己の快楽を目指すことにのみ集中しだしていた。 「イく……イ、ヒ、イく……イく……」 うわ言のように、その口から喜悦の言葉が漏れる。すると、その様子を見ていた緑川が言った。 「おい、もうチンポはいいのか? 指チンポでイくか?」 決して本気ではなかったろうが、やや嫉妬を感じはしたらしい。猪突猛進なこの盛りのついた飼い犬をしつけるべく、彼は冷静な判断で、再び自身の陰茎への興味を喚起させようとした。 「あ……あ……」 顎を上げ、小鼻を膨らませる祐子。やがて、腹から搾り出すような声で言った。 「欲しい……!」 言ってから、唇を内側に入れて、その表面を湿らせる。いかにも食い意地の張った仕草だ。 「へっ――、じゃあ入れてやるか」 鼻で笑って、緑川は彼女を突き飛ばすようにして仰向けにさせると、その股へと肉棒を近づけていった。ゴクリと生唾を飲む祐子。と、ここで、緑川がふいに、意表を突く質問をしてきた。 「もうゴム着けなくていいよな?」 「え?」 祐子ははっとして、その刹那我に返った。実のところ、この確認をされるまで、避妊具の有無に気が付かなかった。もし指摘されなければ、何の疑問も持たずに受け入れていただろう。それほど、彼女は舞いあがっていたのだ。 「もういらねえだろ、コンドーム。生でやらせろよ」 緑川は、その固い突起で陰唇を突っついてくる。祐子が意識しなくても、膣口はその突起を勝手に吸いこんでしまいそうだ。激しい煩悶が彼女を襲う。 (生で……?) それこそ本来のセックス、すなわち子作りのための性交渉を意味する。だが祐子は、これまでそれをしたことがなかった。子作りをしていながら、避妊をし続けてきた。人間ならではの矛盾、エゴなセックスである。 努素毛部屋での数々の淫行も、常に妊娠の危険を回避しながら行ってきた。それは、相手方の方でも推奨していることだった。いつでもコンドームが常備してあるあたり、いづ美もそのようにしているのではないだろうか。 「あんたも生の方が気持ちいいんだろ?」 彼女の逡巡を愉しむように、緑川がけしかける。 (生……気持ちいい……) これまで意識にのぼらなかったことが、とても重要な意味を帯びて彼女の心を占めていく。これまでは、特にこだわりもしない一方で、当たり前のこととして避妊をしてきた。それは、現在の立場になる以前からのことだったが、やはり世間の注目を浴びるという職業柄からも言えることだった。仕事には、プロ意識の強い彼女である。 だが、今まで考えもしないことだったが、避妊具を着けるのと着けないのとで、快感に差があるように彼は言うのである。彼女の心は揺れた。あまつさえ、体は極限の状態で男を欲している。 (今回だけ……) 祐子はぐっと股を開いた。無論、いつぞやのように、今回もやはり前途が闇に閉ざされているとの諦観が後押ししているのは確かだ。 「して……」 ついに彼女は言った。自分の子の父親を決定するかもしれない重大な決断だったが、何の臆面もなく言った。決して子供を産みたかったのではない。ただただペニスを入れてほしかっただけである。祐子は浅薄な女だった。 そんな彼女にカメラを向けて、緑川は詰め寄る。 「何してほしいか、はっきり言いな」 そのレンズを見つめ、祐子は言った。 「入れていいです……おチンポ……コンドームなしで……」 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |
|
「アッ……ン……」 愛液の溢れる泉に、ズブリズブリと中指を沈めていく。いわゆる“外派”より“中派”の彼女にとって、深々と指を挿し込んで動かすことは極めて自然な流れだった。 しかし、そう無意識に行ったことが、緑川からの意外な指摘を招く。 「慣れたもんだね。ズブズブ指入れてさ」 祐子ははっとして手を止めた。何も考えず自然のままにやったつもりだったが、思いがけず変態的なやり方だったのだろうか、彼女はたちまち不安になった。 「そりゃそうか。こんだけヤリマンなんだもんな。そりゃ普段から我慢できないわな」 続けざまに放たれた彼の台詞を受け、祐子の顔がカーッと火照り出す。手淫の癖があることも、そしてそのやり方も、何もかも他人に知られてしまったことに、改めて恥じ入る。 そもそも、彼女にとって最も隠しておきたい習慣を、人に明かすどころか眼前で披露するなんて、そんな日は一生来ないと考えていた。物心ついてから今日までひた隠しにしてきた因習、もはや彼女のパーソナリティーの中枢であるそれを、打ち明けるなどということは。 祐子はその動揺を悟られないために、眼前の肉茎に唇をかぶせていった。すると、すかさず緑川が、 「口は使うな。においだけでオナれ」 と、彼女の行為を拒絶する。これで目論見を阻まれた祐子は、卑屈な気持ちになって、言われた通り陰茎のにおいをかぎながら、指の摩擦を続けた。 「いつも一人でやってんの」 話を戻す緑川。結局、自慰の話からは逃れられない定めらしい。 「昨日もやったのかよ」 祐子は返答しない。すると、彼はそれを肯定の意味と勝手に決めてしまった。 「そうか、やったのか。どうせ今日のこと想像しながらやったんだろう」 彼は言った。実は図星だった。元来、毎日でもここに来たい彼女なので、日々我慢の連続ではあったわけだが、いよいよそれが限界という所で、ここへの訪問を決めたのだった。それで、決定してからは、来たるべき日のために制限しようとも思いながら、それへの期待感から、結局前日も夜中までオナニーに耽ってしまったのである。 「どんだけ変態なんだよ。――あんたさあ、アナウンサーなんかじゃなくて、AV女優にでもなればよかったのに。乳もでかいしさあ」 情けなさを噛み締めながら、祐子は彼の言葉を聞いていた。不思議なもので、彼に言われると、自分でもそれが正しい選択ではなかったかと思えてくる。体を売って、快感とお金がもらえるなら一石二鳥ではないかと。彼女はいつしか、体面という大事なものを失念していた。 一方、指先は日常の動作を決して失念したりしない。性感ポイントを的確に押さえつつ、堂に入った動きで淫唇を慰めていく。その口は、粘液でチュパチュパと音を出しながら、主人の指に夢中でむしゃぶりついていた。 「そうだ」 急に緑川が言った。何か思いついた様子だ。 「エロいオナニーでさあ、俺のチンポ勃起させっぱなしにできたら、入れてやってもいいよ」 瞬間、祐子の目は爛々と輝きだした。やっぱり欲しい。入れてもらえるなら、それ以上のことはない。何といっても、本物だ。彼女の痴態は勢いを増していった。 挿入する本数を、一本から二本へ、二本から三本へと増やす。もっとも、これはいつもやっていることだ。基本的に、直接肉体が感じる気持ちよさは、一本で十分ではある。が、二本も、三本も入れてしまっている、という意識が、精神的な快感を呼び起こすのである。 「うっわあ、すげえな。どんだけ指入れんだよ」 早速緑川が反応する。果たして、これは彼にとって加点対象となるのであろうか。自分で自分の膣に三本も指を入れる女は、果たして報われるのであろうか。 当然、祐子としては報われたい。彼女は、目標である一点だけを凝視しながら、狂ったように淫口をかき回した。それにつれ、ヂャブヂャブと愛液の音が鳴る。 “エロいオナニー”それがどんなものなのか、その答えは分からない。そこで、とにかくがむしゃらに淫乱な様を見せつけることした。 それは、もちろん目的の物を獲得するためにほかならなかったが、同時に全てをさらけ出してしまいたいとの欲求にも適うものだった。オナニーという、自分にとって最大の秘密を暴露した今、いっそとことんまで淫らな自分を告白してしまおうと考えたのである。 「おうおう、自分で乳まで揉みだしたぜ」 笑いながら、緑川は携帯のカメラを彼女に向けた。右手で股間を、左手で乳房をいじくる祐子が、レンズに収まる。 彼女の手淫は、今や通常のそれと変わらないものになっていた。乳房を揉んだり、乳首をいじめたりするのも、日常で彼女がやっていることである。もちろん、普段はトイレの個室などでこっそりとしているわけだが。 「アァ……ハアァ……」 ついに、淫らな声まで出し始める。これも、自室で行う折などにはよくしていることだ。声を出すと、俄然気持ちが盛り上がるのである。 だが、今日はこれだけでは弱いと思ったのだろう、何しろ“エロいオナニー”をしなければならないのだ。そして、真の淫乱な己を見せてしまいたいのだ。彼女は、段々と声のボリュームを上げていくと、そのうち卑猥な文句まで交え始めた。 「ハァ……アァハ……き、気持ち、いい……マン、コ……ゆ、指っ、指チンポッ!」 あられもない言葉で、とうとう彼女は、長年秘めてきた恥辱を吐露した。 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |
|
「けど、あんたさあ、テレビ出る人間のくせに、よく顔にザーメンぶっかけさせたりできるよね」 緑川は早速口撃を始める。彼が言わんとしていることは、例によって、日常の彼女の評判を貶めるものであった。 それにしても、確かに指摘の通り、顔面をセックスに使わせるというのは、相変わらずの彼女の迂闊さではある。彼女とて、自分のパーツの商品価値を把握していないわけはないはずだが、それでも求められれば受け入れてしまうのである。 あるいは、彼女のマゾヒズムが、返ってそうやって自分の大切な部分を穢させようとしているのかもしれない。顔に精液をかけられるというのは、一般の女性にも屈辱的なものに違いないが、この場合有名人として特別な価値のあるそれをさし出すことによって、より強烈な性的興奮を得ようとの精神の働きというわけである。 「なあ、顔マンコ」 今やすっかり定着した愛称で呼びかけながら、緑川は自身の陰茎を露出し、それを彼女の頬に乗せた。そして、その図をカメラに収める。 (あぁ……) 倒錯した感情が、祐子をよろめかせる。一つには、著名人としての自らの将来が、またもや奪われるかもしれないという危機感、かつ一方で、それほどまでに自分を追い込んでいるとの意識からくる理不尽な高揚感。 それらあらゆる感情は、最終的に、ズシリとのしかかってくる陰茎の重みによって、一つの自堕落な方向へと押し流されていく。 (重い……) ペニスは重い。だがその重さが心地いい。白木の場合もそうだが、この重さがどれだけ女にとって憧れであり、安らぎを与えてくれることか。頬にそれを感じるだけで、一種恍惚となってしまうほどである。 さらに、それで顔面を犯されること、それはもはや幸せをすら感じさせるものだ。ただ、今日の場合、犯されるというのとは些か状況が異なるようだった。 「この顔使ってさ、勃たせてみろよ」 彼は言った。その趣意は、顔で男根を愛撫しろということである。 既に今日は二本の男根を経てきたこともあって、加速度的に性に開放的となっていた祐子は、もはやこんな破廉恥な命令にもたじろがなかった。つい先ほど、ビンタをされてショックを受けたこともあったが、逆にそれがトラウマと被虐嗜好を目覚めさせたものとも見える。 陰茎は、まだ平常の状態だった。挿入するには、いずれ勃起させなければならない。そういう合理的観測も背景にあった。 祐子は、ゴクリ、と生唾を飲み込むと、やがてズリズリとやりだした。両手でそれの根元を支え、頬にこすりつけ始める。“顔を使って”の意味を、瞬時に理解した彼女だ。顔面を性の道具に用うるという認識は、すっかり常識であるらしい。 だがその実行の仕方は、まだ緑川の気に染むものではなかった。 「手を使うな」 号令一下、祐子は両の手を背中に組まされた。まさに、顔だけで陰茎を愛撫しろというわけである。彼女は言われた通りにした。正座に近い姿勢で前のめりになって、股間に突っ伏していく。その格好は、傍から見ると異様で、かつ間の抜けたものだった。 陰茎は、顔の上を端へ端へと逃げ回る。勃起していないそれは、手で固定しない限り安定しないのだ。よって、中々しごくという動作にまで至れない。それでも彼女は、懸命にそれを行った。そうすることで彼への忠誠を示したかったし、他方、コリコリと感じるその感触が心地よかったからである。 しかし、祐子の満足がイコール緑川の満足とはならなかった。 「そんなんじゃ勃たねえよ。もっと考えろ」 彼は命じた。祐子は言われた通り考え、そして一つの結論を出した。口を開き、舌を伸ばす。チロチロと、それで肉茎を摩擦しだす。フェラチオの一環である。だが、相手はその営業努力のさらに上を要求してきた。 「よぉし、それやりながら顔でコけよ」 祐子は、舌で陰茎から陰嚢までを舐めつつ、顔にそれらを押し付けてこすることにした。たちまちのうちに、顔中唾液まみれになる。 「へっへ――あんたマジで顔マンコだな。チンポ専用の顔だわ」 緑川の、そんな意地悪な台詞も、今や彼女を辱めるには至らなかった。彼女はもう、夢中で男の股間を顔面愛撫していた。むせ返るような男のにおい、獣を思わせるそのにおいが鼻腔から肺に充満していく。唾液の海には、いつしか精液の先走りが混じりだしていた。それに伴って、柔らかかった突起が、次第に太り固さを増していく。 (素敵……) みるみるオスのあるべき姿へと成長を遂げていくペニス、自分の顔で育て上げたペニスだ。祐子は、誇らしさと嬉しさを感じながら、立派になったそれを慈しんだ。 (あぁ、おチンポ……わたしの顔マンコで大きくなって……) 完全に顔面を膣に見立てた交尾を肯定し、祐子は狂おしく男根と戯れる。既に念願の勃起は達成されていた。となると、顔面交尾もいいが、やはりあるべき場所にそれを迎え入れたい。何しろ、絶頂は確約されている代物なのだ。 (欲しい、欲しい――) お預けを食わされる犬のように、チラチラと主人の方を窺う祐子。精嚢に鼻を突っ込めば、そこはいかにも精液が詰まっていそうにズシリとして、否応なしに期待を煽られる。彼の体も、とうに準備万端のはずだ。もちろんメスの体は、いつでも合体オーケーである。 ところが、そんな彼女を待ち受けていたのは、緑川の非情な一言だった。 「やっぱ今日やめとくわ」 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |
|
そして、ゼエゼエと肺からの深い息を交えながら低い声で喘ぐ。 「アア……アア……アア……」 快感の向こう側で得られる、深い満足の時間だ。焦らされたせいか、追い詰められたせいか、いつも以上に満足の度は大きかった。しばしぐったりとなる。 緑川はその様子を見下ろしていた。 「イきやがった――白木、お前は?」 ふと後輩の方を見る。それを急かされたと感じたのだろう、白木は、 「あ、もうちょっとで……」 と言いざま、猛烈に肉棒のピストンを送り込みだした。 「アッ、ンッ、アッ――!」 オーガズムに達したとはいえ、男に突かれれば、惰性で悦んでしまうのが女の体だ。祐子は、こんもりと盛った尻肉を震わせながら、その悦びに酔いしれた。 それを一瞥しながら、緑川は、白木の思惑とは違って意外な注文をつける。 「お前、イく時、顔に出してやれよ。好きだろ、顔射」 彼は、後輩がそういう趣味のあることを知っていた。 「あ、はい」 反射的に答える白木。それは、先輩の命令が絶対だったからだが、内心では少し照れていた。いつもねだってやらせてもらっているとはいうものの、改めて他人に指摘されると恥ずかしいものだ。とはいえ、結果として願ったりかなったりではある。 彼は、十遍ほど素早く腰を振ると、最後に三発、バチンというけたたましい音を響かせて相手の尻を引き寄せ、やがてそそくさとゴール地点へと向かった。そして、装着していたコンドームを引っ張って取り外す。 「おい、顔上げろ」 一方、緑川は祐子の後頭部をつかんで、白木のためにお膳立てをしてやる。 「今から顔にザーメンぶっかけてやるからな」 彼は言って、カメラをセットした。彼が撮りたいのは、女子アナが顔面に精液をかけられる映像だった。 「へっへ、やっぱ、この顔使わねえとな。この商売道具をさ」 彼の言う通り、テレビに出る人間にとって、顔は商売道具にほかならなかった。その美醜が多額の価値を生む。彼の目的は、その価値を貶めることにあった。 「もう散々かけられてるんだろ、な? 顔面まで精液便所だな」 その台詞には、性器は元より、という意味が前提として含まれていた。実際、男たちの性欲の受け皿になっているのだから、言われる通りかもしれない、そう思う彼女には、もはやからかわれることによって動く心の持ち合わせが何もなかった。 「そんな汚ねえ面でよくテレビ出るよ。ザーメン顔でさあ。なあ?」 緑川は、またしても祐子に、彼女の仕事と立場という現実を一々喚起させた。すると、それが肉欲で温まった肉体と相まって、彼女に一層自分を諦めさせていく。 「謝った方がいいんじゃねえの? これ見てる人にさあ」 彼は言った。まったく根拠のない理論である。相手が罪人であることを前提に、野次馬が調子に乗って無責任に非難する時の論調だ。 だが、祐子はうなだれて言った。 「すみません……」 あっさりと謝った。彼女にはもう何も考えがなかった。 それをいいことに、緑川はさらなる謝罪の言葉を要求する。と同時に、白木に合図して、彼にいよいよ射精を促す。 白木は肉茎をしごきながら待っていたが、指示を受けて、その先端を的へと向けて近づいていった。そして控え目に一歩前で止まる、と、緑川に、もっと近付けと言われ、さらに進み出る。結局、祐子の鼻柱の脇に、亀頭を押し付ける形になった。 一方の祐子は、それを拒みもせず、緑川に吹きこまれた謝罪の台詞を、ただひたすらしゃべっていた。例によって、何度も何度も言いなおさせられながら。 「番組中、不適切な顔がございました。大変失礼致しました」 職業柄慣れ親しんだ表現で、謂れのない謝罪をする祐子。その表現は、さらにエスカレートしていった。 「いつもお見苦しい顔をお見せして、誠に申し訳ございませんでした」 自分を捨てた彼女は、どんな台詞も求められるままに言った。 「わたくしの顔は、精液のお便所です。男の人に射精してもらうための場所です。マンコです。マンコ顔です」 下らない称号も難なく受け入れていく。 「今までこんな顔でテレビに出て、本当にすみませんでした。私の顔は猥褻物です。私の顔は放送禁止です……」 そう話す彼女の頬を、涸れていたはずの涙がはらはらと流れ落ちる。表の態度とは裏腹に、体に刻まれていた深い喪失感が、本人にも無自覚に発露したものだ。それと同時に、股間からは粘ついた汁が湧いて出る。 「私は顔で交尾します。顔でおチンポしてもらいます。おチンポの顔です。顔面性器です」 そう話す彼女の上を、実際に白木のペニスが行き来する。彼は自身でしごきながら、いつしか相手の顔でもそれをこするようになっていた。まさに、顔面との交尾だ。 この顔でそんなことをされるとは、日頃の視聴者の一体誰が想像できたろうか。アナウンサーといえば、ニュースを読む間一人で画面を占拠する場合が多いが、それが全面猥褻映像に変わるというのだから、彼女の顔が猥褻物だというのも、あながち見当違いではないのかもしれない。 今しもいきり立った男根は、ベトベトにまとわりついた粘液を泡立てさえしながら、柔らかい頬や小鼻、唇、時には髪の毛をも巻き込みつつ、縦横無尽に祐子の顔を犯す。ここぞとばかり無茶苦茶に彼女をいたぶる白木は、いつになく乱暴だ。 「フ、ンワ、ア……」 固い肉棒と粘液の圧迫で、祐子は息苦しくなる。それほどの凄まじさだ、白木ももちろん射精感を昂らせていた。 「かけて下さい。祐子のどスケベな顔マンコで、イッてください! お願いします。顔マンコでイッて……」 そう彼女が懇願した時だった。 ――ビュッ! 勢いよく、鼻筋を右から左へと、熱いほとばしりが横断した。立て続けに、二波、三波が、頬や唇にこぼれ落ちる。たちまちのうちに祐子の顔は、ドロリとした白濁液で彩られていった。 白木はその吐き散らかしを、なおも塗りたくるように腰を動かし、ようやく離れた。離れる時には、白い糸をダラリと引いていた。 「ありがとうございました。おチンポに顔射してもらいました。祐子のザーメン顔を見て下さい」 祐子は言った。精液のついた顔をカメラに見せながら。その頬は上気していた。 「私の顔はザーメンくさい顔です。精液のにおいが取れません。私の顔は、おチンポのにおいです。私は……私の顔は、マンコです……」 鼻腔に強烈な男臭さが入り込んでくる。彼女はそれを嗅ぐと同時に、先ほど来の余韻の延長で、じんわりとエクスタシーに達した。精神と肉体が混然一体となったエクスタシーだった。 彼女は最後にこう言った。緑川に言わされたのでありながら、妙に真実味のある言い方で。 「こんな顔マンコですから、もうニュースは読めません。顔マンコの私には、もうニュースは読めません……」 こうして彼女のレポートは終わった。彼女のアナウンス人生も、終わった。 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |
|
それは、生来の淫乱である祐子ならではの解答だったろう。あまつさえ、欲情しきった体と、捨て身の覚悟を備えている折りも折りだ。 「イきたいのかよ?」 緑川は重ねて問うた。祐子は再び頷き返す。それを見ると、彼は相変わらずニヤニヤしながら、白木に向かって指図した。 「祐子さん、イきたいんだってさ」 それを聞くと、白木は今一度腰を前に進めた。が、緑川はなぜかそれをとどめてしまう。その上で言うには、 「指でイかせてやれよ」 祐子にとっては期待外れもいいところである。別にただオーガズムに達しればいいわけではない。むしろ男を迎え入れられれば、達しなくてもいいぐらいだ。 (うそ……) 残念がる彼女を尻眼に、白木は実際に指で彼女の陰唇をいじくっていく。 「ア……ンフ……」 快感的刺激は確かにある。しかし、欲しいのはそれではない。にもかかわらず、指の愛撫によって、刻々と絶頂に近づいていく。 (や……だ……ア……イ、く――) 彼女は、極めてしまった。静かに、そして不本意に。 しばらく見守ってから、緑川が声をかける。 「イッた?」 祐子は答えなかった。申告したくなかったし、不満でもあったから。すると、緑川がこんなことを言ってきた。 「ちなみにだけど、チンポまだ立ってるみたいだけど――」 一筋の光が雲間から見えた、気がした。祐子は耳を尖らせて、次の文句を待つ。 「あいつイくまでさ――」 祐子はゆっくりと顔をあげていく。返事の準備は万端だ。 「続ける? 撮影?」 ――がっくりときた。“撮影”――まだ抵抗感は否めない。が、彼女は頷いていた。それは果たして彼女なのか、別人が勝手に下したような判断だった。言い訳にすがらざるをえない女という生き物は、時にそんな無茶な仮定までする。 「じゃあ、こっち向いて言って」 緑川は、そう言ってレンズを向けてきた。祐子は反射的にそちらを見、慌てて視線をずらして上目遣いに彼を窺う。 「カメラに向かって言いなよ」 彼は悪魔のように囁いた。 「“チンポ入れて下さい”って」 (あ……あ……) なんとバカバカしく、なんと破廉恥な行為だろう。祐子はその愚かしさに呆れた。だが彼女は、彼に輪をかけて愚か者だった。 「お願いしないとやめるぜ?」 彼に急かされて、彼女の口はひとりでに動き出した。 「チ、チンポ、い、入れて……」 言った途端、カーッと顔中が熱くなった。自分の声が自分のものと思えない。なんて下らないことを言っているのだろうと、彼女は己に驚き呆れた。今の羞恥は、自分に対する嘲笑から生まれるものだった。 そんな彼女に、緑川はやけに優しげに、そして残酷に言い放った。 「え? なんて? もう一回言って。今度はカメラ目線でさあ」 性悪極まる台詞だった。だが、そうと分かっていながら挑戦するのが愚か者である。 「チン……ポ、入れ……て、く、くだ……さい……」 そう話す唇、眼差しが、フレーム一杯に収まった。インタビューに答えるように、祐子は今、男根の挿入をカメラに向かって宣言していた。 しかし、緑川はそれでも納得しない。 「声ちっちゃい。それに、カミカミじゃん。それでもアナウンサーなわけ?」 確かに、さっきの言い方では、アナウンサーとしては不適である。普段なら、到底あり得ない発声・発音だ。曲りなりにも、祐子はアナウンサーである。緑川は、意地悪くもそんな現実問題を突きつけてきた。 「チンポ……い、入れて下さい……」 結局また言わされた。別に職業上のプライドからではない。できれば言いたくなんかない、彼女はそう強く心に叫んだ。が、 「もう一回」 非常にもオーケーは出なかった。彼は監督にでもなったつもりであろうか。だとすれば、祐子は差し詰め、ポルノ映画の主演に抜擢された女優といったところか。 「チン、チンポッ……入れて、下さ、いっ……」 彼女は繰り返した。すると不思議なもので、声に出す度に、それが現実となって重くのしかかってき、まるで暗示にかかったように、気分が高揚してくるのである。羞恥は依然ある、が、それも含めて受け入れられるようになってくるのだ。彼女はますます、奴隷のような根性に染まってきた。 <つづく> <目次> (1)~(10)、(11)~(20)、(21)~(30)、(31)~(40)、(41)~(50) (51)~(60)  |